高止まりする電気料金に対する考察
ここ最近、電気料金の高騰が家計を直撃しています。テレビや新聞でも連日のように報じられており、特に燃料費の高騰がその大きな要因とされています。ウクライナ情勢や中東の不安定化により、原油や天然ガスといったエネルギー資源の価格が世界的に上昇し、それがそのまま私たちの電気代に反映されているのです。
しかし、私たちの電気料金を押し上げているのは、国際情勢だけではありません。実は「再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)」という制度が、私たちの電気代に上乗せされています。
この再エネ賦課金とは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの普及を目的として、電力使用量に応じて国民全体から徴収される仕組みです。制度自体は、地球環境に優しいエネルギーの普及を促進し、脱炭素社会を目指すという趣旨で導入されました。
しかし、その負担は決して小さなものではありません。2025年度の賦課金単価は1kWhあたり3.98円が予定されています。一般家庭では月に300kWh程度を使用するとして、単純計算で毎月約1,200円、年間にして14,000円以上の負担となるのです。特にオール電化住宅に住んでいるご家庭では、これが月に数千円にも膨らむ可能性があります。
果たして、私たちはそこまでして再生可能エネルギーを普及させるべきなのでしょうか。再エネは本当に、そのように税金のようなかたちで支えられなければならない存在なのでしょうか。もし、そこまでしなければ市場で生き残れない電源であるならば、それは本来、競争原理に基づく電力市場に適していないのではないかという疑問が湧いてきます。
実際、太陽光発電においては、個人や企業がそれぞれの思惑で発電事業に参入・退出を繰り返しており、そのたびに送電網への接続や電力の品質確保といった課題が電力会社の負担としてのしかかっています。本来、電力というものは、安定して届けられることが大前提であり、それを支える送電インフラには、十分な計画性と責任ある運用が求められます。
そうであれば、やみくもに再エネを推進するのではなく、例えば発電設備の設置には事前届け出制を導入するなど、地域全体を見据えたエネルギー計画のもとで整然と組み込まれるべきではないでしょうか。そうすることで、電力網全体の最適化が進み、無駄のない持続可能なエネルギー供給が実現できるはずです。
そして、こうした合理的なエネルギー政策が進めば、今私たちが負担している再エネ賦課金も不要になる可能性があります。すなわち、電気代の引き下げにつながるのです。
再エネを推進することそのものに反対するわけではありません。しかし、その手段が適切であるか、今の制度が国民にとって公平かつ合理的であるかという視点は、今こそ真剣に問われるべきです。私たちは、外資系の再エネ事業者の利益を支えるためにお金を払っているのではありません。もっと身近な、自分たち自身の生活を守るためにこそ、お金は使われるべきではないでしょうか。
このような問題意識が広がり、政治を動かす原動力になっていくことを願います。国民民主党の玉木代表は、再エネ賦課金の廃止を公に訴えています。こうした主張に対して、もっと多くの国民が関心を持ち、議論を深めていくことが必要ではないでしょうか。
さて、皆さんはこの再エネ賦課金について、どうお考えになりますか?
未来のエネルギーをどう支えるべきか、そろそろ私たち一人ひとりが真剣に考えるときが来ているのかもしれません。

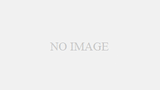
コメント